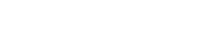Monozukuri Ventures(以下、MZV)代表の牧野です。 Monozukuri Venturesは、2015年8月の創業からちょうど10年を迎えました。節目の年に当たり、これまでのあゆみを振り返りつつ、これからに向けた展望を書いてみたいと思います。
原点──なぜMZVを始めたのか
私は学生時代から「スタートアップが新しい世の中を作る」と信じ、スタートアップに関わる仕事がしたいと考えました。そしてもう一つ、「地方からスタートアップが起こるような環境づくりにも貢献したい」と考え、京都・関西を拠点にキャリアをスタートさせました。 2005年に京都を中心に地方自治体等と連携して地方のスタートアップ支援を行うフューチャーベンチャーキャピタル(現ミライドア)に就職、2011年からはシリコンバレーに拠点を持つサンブリッジに転職。スタートアップ投資に加えて、大阪のスタートアップエコシステム構築にも携わりました。 京都や大阪でスタートアップに関わるなかで、地域の強みを活かしたエコシステムの重要性を感じるようになりました。そんな想いから関西の特長の一つである、「モノづくり」をベースとしたVCの可能性を感じるようになりました。 もともと起業家(=挑戦者)が輝ける社会を作りたいという想いが根底にあり、その中でモノづくり領域は「Hardware is Hard」と課題が多く残っていました。だからこそ、モノづくりの起業家が輝ける社会「モノづくりは、簡単だ」というビジョンが誕生しました(もちろん創業当時は明文化されていませんでした)。 そのビジョンの実現を目指して2015年8月にMonozukuri Venturesは誕生。 今月でちょうど10年の節目となりますが、振り返ると4つのステップを経て成長してきました。
MZV10年の軌跡
・1stステージ(2014年〜2017年):京都試作ネットと連携した試作支援のサービス開始 ・2ndステージ(2017年〜2020年):試作と資金を支援する投資サービス開始 ・3rdステージ(2020年〜2023年):米国FabFoundry社との経営統合と北米展開の加速 ・4thステージ(2023年〜):日本の製造業のオープンイノベーション促進 詳細はMZVの軌跡とこれから – 製造業のオープンイノベーションに貢献 –を参照
進化するMZVの現在地
現在は日本、アメリカ、カナダに拠点を持ち、投資事業、試作支援事業、オープンイノベーション事業の3つを柱としています。試作支援では250プロジェクトを超え、投資先は日米58社となりました。またオープンイノベーションでは大企業向けにスタートアップとの連携プラットフォーム「モノづくりイノベーションラボ」を立ち上げ、そのベースとなる製造業のクローズドコミュニティ「MIサロン」も全国に拡がりつつあります。

これからのMZV──連携と挑戦が生む新しい流れ
現在、MZVは第4ステージとして「日本の製造業のオープンイノベーション促進」に取り組んでいます。 まだ課題はありますが、大企業等との連携やM&Aに向けた基盤は着実に整いつつあります。 また、創業当初から力を入れてきた中小企業等と連携した試作支援も着実に成果が見え始めています。 「モノづくりは、簡単だ」というビジョンに向け、スタートアップが成長するためのサプライチェーンとバリューチェーンの両方が整いつつあります。 これからの課題は、こうした体制の中で既存投資先の成長をさらに加速させ、Exitを出していくことです。さらに米国での投資を強化し、モノづくり(ハードウェア、ハードテック、ディープテック)のスタートアップの創出やモノづくりに適した新しいコンセプトのファンドにも挑戦していきたいと思っています。
ネットワーク構築という壁
私にはもともと「地方からスタートアップ創出に貢献したい」という想いがありました。 しかし実際には、お金や試作支援だけでなく、起業家やスタートアップを支える人材面のネットワークづくりなど多大なエネルギーが必要で、私達には限界がありました。 最大の課題は起業家や起業家候補とのネットワークでした。 京都では特に、京都大学など大学とのネットワーク構築が鍵になります。さらに、大学と繋がるだけでは不十分で、その技術シーズをベースに創業チームを作れるかもポイントでした。 これらは地方の小さなVCには難しいテーマでしたが、2024年、京都大学でロボットやAIを研究する谷口先生と共に「Tomorrow Never Knows」という大学の技術シーズを社会実装するための社団法人を立ち上げ、大学との繋がりを作ることが出来ました。いまこの組織には社会を変革する新しい技術や研究者が集い始めています。 もう一つの課題である創業チームの構築です。 この分野では、パソナマスターズ社と連携し、これまでにはないスタートアップ経験者の流動化を促す取り組みも進んでいます。
長期運用型ファンドへの挑戦
もう一つの挑戦は、モノづくりスタートアップを支える新しい形のファンドへの挑戦です。 これまでMZVは「モノづくりは、簡単だ」というビジョンのもと、モノづくりスタートアップの成長を加速する取り組みを推進してきました。 背景には、「ベンチャーファンドは10年間で結果を出す」という一般的な仕組みがあります。 しかしモノづくり領域では、10年間はあっという間。事業の成長スピードとファンドの運用期限との間に、大きなギャップがあることに悩んできました。 12年や18年といった長期ファンドを検討したこともありましたが、何となくその期間に根拠もなく、もっと斬新なコンセプトが必要だと感じていました。
関西から発信する新しいベンチャー育成の形
そんな時、京都経済同友会のスタートアップ研究委員会と「これからの京都のスタートアップエコシステムのあり方」について情報交換する機会がありました。 京都経済同友会は私にとっては特別な存在です。 日本初のVC「京都エンタープライズディベロップメント(KED)」は同組織によって1972年に設立されており、そこから日本のVCの歴史がスタートしています。約半世紀を経た今、再び京都/関西から新しいスタートアップエコシステムやファンドのあり方を発信する使命を感じています。 ちょうど同じ時期、ある尊敬する経営者から「京都は長い歴史があり、100年先を見ているんだから、そのぐらい長期運用するファンドを考えてみては?」とアドバイスされました。 その時は実現が難しいと思っていましたが、2021年にはシリコンバレーでSequoia Capital(セコイアキャピタル)が、運用期限のない「エバーグリーンファンド」という新しいファンドを発表。世界的にも長期運用する流れも生まれつつあります。 日本でも令和6年の金商法改正で、セカンダリー投資の規制緩和や投資信託による未上場株式取得が解禁がされ、従来のベンチャーファンドの常識を見直す好機が訪れています。
この先も挑戦は続く
この10年間を振り返ると、本当に「あっという間だった」でした。同時に、当初目指していた会社の姿には遥か及ばず、悔しい想いの方が強いです。 ただ、今の私達が出来ることはこれまでの土台をベースに、如何に社会に貢献出来る存在になるかです。これから先に何が起こるかは分かりませんが、その時その時を一生懸命に生きることが大切だと思っています。 未来はわからないことだらけですが、10年後の2035年にまた振り返ることが出来たらなと思います。 【参考文献】 ・Tomorrow Never Knowsの概要はこちら ・京都エンタープライズディベロップメント(KED)に関して 濱田、桐畑、片川(2006)「我が国ベンチャーキャピタルの投資実態」
Monozukuri Venturesでは、ハードウェア・ハードテック特化型のVCからみた、製造業・ハードウェア業界動向のご紹介をしています。ご興味のある方はこちらの当社ニュースレターへご登録下さい。

Monozukuri Ventures CEO。愛知県出身、京都に住んで17年。ずっと関西中心にスタートアップに関わる仕事をしています。今は京都の梅小路エリアにてスタートアップ、アーティスト、クリエイターが集うような街づくりにも挑戦中。2児の父親として育児も頑張ってます!!