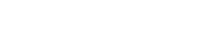Monozukuri Ventures(以下、MZV)代表の牧野です。
前回のブログでは、「スタートアップとのオープンイノベーションの取り組み方」に関して紹介しました。今回は、京都府とともに取り組んでいる「京都アクセラレーションプログラム(以下、KAP)」についてお話したいと思います。このプログラムは「カーブアウト」を視野に入れた外部リソースを活用した大企業向けの新規事業創出プログラムです。先日、KAPのDemo Dayを開催しましたが、「KAP誕生の背景や裏話」についてお話したいと思います。少しでもオープンイノベーションを進める参考になれば幸いです。
KAPとは?
KAPは京都府をはじめとする京都アクセラレーションプログラム実行委員会とともに行っている、外部リソースを活用した大企業向けの新規事業創出プログラムです。2021年にスタートして本年2回目を迎えました。企業は常に新規事業を創出し続ける必要がありますが、社会の環境変化が激しい中にあって、社内のリソースのみで新規事業創出をすることに難しさを感じているようでした。 スタートアップと普段関わっているわたしから見ると、 ・スタートアップと同様に社外のリソースも活用し ・かつカーブアウトとして切り出すやり方 は、これからの大企業の新規事業創出の一つの手段になると感じることがありました。 そこで「大企業からもアントレプレナーの輩出に貢献する」をミッションにKAPはスタートしました。
KAPが始まったきっかけ
私たちが大企業向けの新規事業創出プログラムを始めようと思ったきっかけは大きく3つありました。

1.muiLab株式会社の大木氏からの学び – VCとの連携
2016年にmuiLab株式会社の代表取締役である大木氏と出会いました。muiLabはNISSHA株式会社からのカーブアウトスタートアップですが、お会いした当時はまだ社内の新規事業にするのかカーブアウトするのか迷っている段階でした。しばらくして、「muiLabへ投資検討は可能か」と相談がありました。その理由を尋ねると「カーブアウトを一つの手段として検討しているが、社内にはカーブアウトの事例がなく、どうすればカーブアウト出来るのかわからない。VCからの出資意向があればカーブアウトの可能性も高まる」ということでした。この理由は理解できたものの、私たち自身が会社になっていない案件への投資検討の経験がなく、「法人化していない案件に投資検討出来ないので、法人化してからまた来てほしい」と回答してしまいました。その後もこうしたやり取りが続き、結果的には2019年5月にNISSHAからMBOする形で独立しました。このときの経験からカーブアウトは、する側(=大木さん)、送り出す側(=NISSHA)、そしてVC(=投資側)とが連携しないと出来ないという事を痛感しました。 以下に詳細が記載されているので興味があれば読んでみてください。 大企業ルールに縛られない。NISSHA発の新会社が実践する「精神的脱藩」とは (muiLab株式会社代表取締役大木氏インタビュー)
2.株式会社島津製作所の新規事業プロジェクトSHIPSからの学び – チームの重要性
私達のファンドの出資者である株式会社島津製作所が、新規事業を進めるためのプロジェクトとして2018年にSHIPS(Shimadzu Innovation Platform with Startups)を発足させました。この取り組みの一環として、社内で新規事業プランのコンテストがあり、わたしがその審査員を務める機会がありました。当初、こうしたプログラムは本業プラスαでの取り組みのため、応募者が少ないのではと思っていましたが、かなりの数の応募があったと聞き、新規事業に取り組みたい人は多いんだと知りました。さらにその時審査した事業プランは既存技術を活用した強みや優位性があり、一般的なスタートアップとは異なる魅力がありました。 一方で以下のようなポイントが気になりました。 ・こうした既存技術に、新しい考え方(ソフトウェア技術やサービス等)が加わると、もっと大きな市場が狙えるのでは? ・その業界に精通した大企業であるが故に既存の価値観に縛られてしまい、柔軟な発想が難しくなっているのでは? このときの経験から、大企業がその分野とは異なる企業や人材と連携することは大きなポテンシャルを秘めていると感じました。
3.ソニースタートアップアクセラレーションプログラムからの学び – 仮説検証の重要性
そして最後に私達MZVの株主であるSSAP(Sony Startup Acceleration Program)からの学びです。SSAPはソニーが2014年に開始したスタートアップ創出と事業運営を支援するプログラムです。これまでは大企業では一定の売上規模等が見込めないと新規事業としてのゴーサインが出なかったようですが、今の時代はどこに市場や顧客があるか分からないため、将来予想が不確実な段階でもプロジェクトを走らせ、その芽をいち早く掴むために始められたプログラムです。 実際にこのプログラムからは数多くのプロジェクトが生まれ、大きな事業に育つ可能性のあるものも生まれているようです。私自身も大企業の方々の新規事業プランの発表を聞く機会がありますが、発表時点でその事業プランを継続するのか、また止めるのかの判断は難しいとも感じました。さらに、その後の判断もなかなか出来ず、いわゆる「塩漬け」になっていることも多いと聞いています。 こうした事例から、事業をすすめるプロセスにおいては、大企業であっても新規事業に関しては、スタートアップでは一般的な顧客のフィードバックを得ながら事業計画を修正していくやり方が有効なのではと思いました。
4.KAPの立ち上がり
大企業での新規事業創出のあり方に関して学ぶ中、2019年に京都府と島津製作所が地域活性化包括連携協定を結び、その項目の一つであった『産業観光(オープンイノベーションが起こりやすい環境づくり)推進』に関して相談がありました。京都には数多くの先進的な企業がありますが、横の連携という点では不十分ということもあり、まずは「企業の枠を超える」必要があるという話になりました。
これまでのmuiLabのカーブアウト事例や島津製作所の社内コンテスト、ソニーの新規事業の課題から学んだこと、そのほかMZVの経験を反映させ、京都らしいオープンイノベーションとして、外部リソース(人材や資金)を活用した新規事業創出プログラム「京都アクセラレーションプログラム」の骨子が作られてきました。
■KAPの3つの特長
①顧客への仮設検証を繰り返して3ヶ月間で事業プランを仕上げる( = 仮説検証による事業計画)
②起業経験者がチームの中に入りゼロイチをドライブする( = チームビルディング)
③VCがデモデイ時に投資検討可否の判断を行う( = 資金調達機会)
KAPの実現に向けて動き出しましたが、「出す人材やアイデアがない」「新規事業アイデアを他社に開示することに抵抗がある」といった理由からすぐには京都企業から賛同は得られませんでした。ただ京都府の方々が粘り強く交渉する中、島津製作所、SCREENホールディングス、そしてマクセルの3社の参加表明があり、2年越しの2021年に第1回としてKAPはスタートを切ることが出来ました。参加企業や参加者から高い評価もあり、2022年10月に第2回目として開始、1月には無事にDemoDayを迎えることが出来ました。そのレポートも作成していますので、是非、ご覧ください。
・Kyoto Acceleration Program Demo Dayレポート
詳細はこちらから
 最後になりましたが、KAPは企業個社への提供を目的としておらず、地域のプラットフォームとして、京都以外にも様々な企業が参加できるプログラムを目指しています。それは「『企業の枠』、『地域の枠』、そして『常識の枠』を超える」ところにイノベーションが生まれると信じているからです。そしてこれこそが京都らしいイノベーションのあり方と考えているからです。こうした取り組みに興味ある方は、ともにイノベーションを起こしていけたらと思っていますので、気軽にお問合せください。
今年度のKAPに関する記事
最後になりましたが、KAPは企業個社への提供を目的としておらず、地域のプラットフォームとして、京都以外にも様々な企業が参加できるプログラムを目指しています。それは「『企業の枠』、『地域の枠』、そして『常識の枠』を超える」ところにイノベーションが生まれると信じているからです。そしてこれこそが京都らしいイノベーションのあり方と考えているからです。こうした取り組みに興味ある方は、ともにイノベーションを起こしていけたらと思っていますので、気軽にお問合せください。
今年度のKAPに関する記事
- Kyoto Acceleration Programとは
- Kyoto Acceleration Programキックオフレポート
- Kyoto Acceleration Program Demo Dayレポート
Monozukuri Venturesでは、ハードウェア特化型のVCからみた、製造業・ハードウェア業界動向のご紹介をしています。ご興味のある方はこちらの当社ニュースレターへご登録下さい。

Monozukuri Ventures CEO。愛知県出身、京都に住んで17年。ずっと関西中心にスタートアップに関わる仕事をしています。今は京都の梅小路エリアにてスタートアップ、アーティスト、クリエイターが集うような街づくりにも挑戦中。2児の父親として育児も頑張ってます!!